
IB EA(External Assessment)の基本|得点アップ法も解説


・IBのEAの対策がよくわからない…
・IAとの違いって何なんだろう?
・子どもにEAの勉強法を説明したいけど、よく理解できてない…
EA(External Assessment=校外試験)はなじみのない試験形式なので、不安材料になりがちです。
この記事を読めば、EAのしくみ・科目別の試験形式・対策を理解できます。
IB専門塾のIBアカデミーなら、世界トップレベルのIB卒業生による個別指導がオンラインで受けることが可能です。
一人ひとりに合わせた学習計画・進捗(しんちょく)管理・希望科目に対応した指導で、EA対策をしっかり進められます。
IB EAの基礎をわかりやすく解説
EAはIBの最終評価への影響が大きいため、とても大切な試験です。
ここではEAのしくみ・IAとの違いをわかりやすく解説していきます。
EA(External Assessment)とは「校外の筆記試験」
EAとは「校外で採点される筆記試験」のことです。
日本の大学入試のように、学校の先生ではなく外部の試験官が答案を採点します。
試験内容は科目によって違いますが、エッセイ(小論文)・長文読解・計算問題などが中心です。
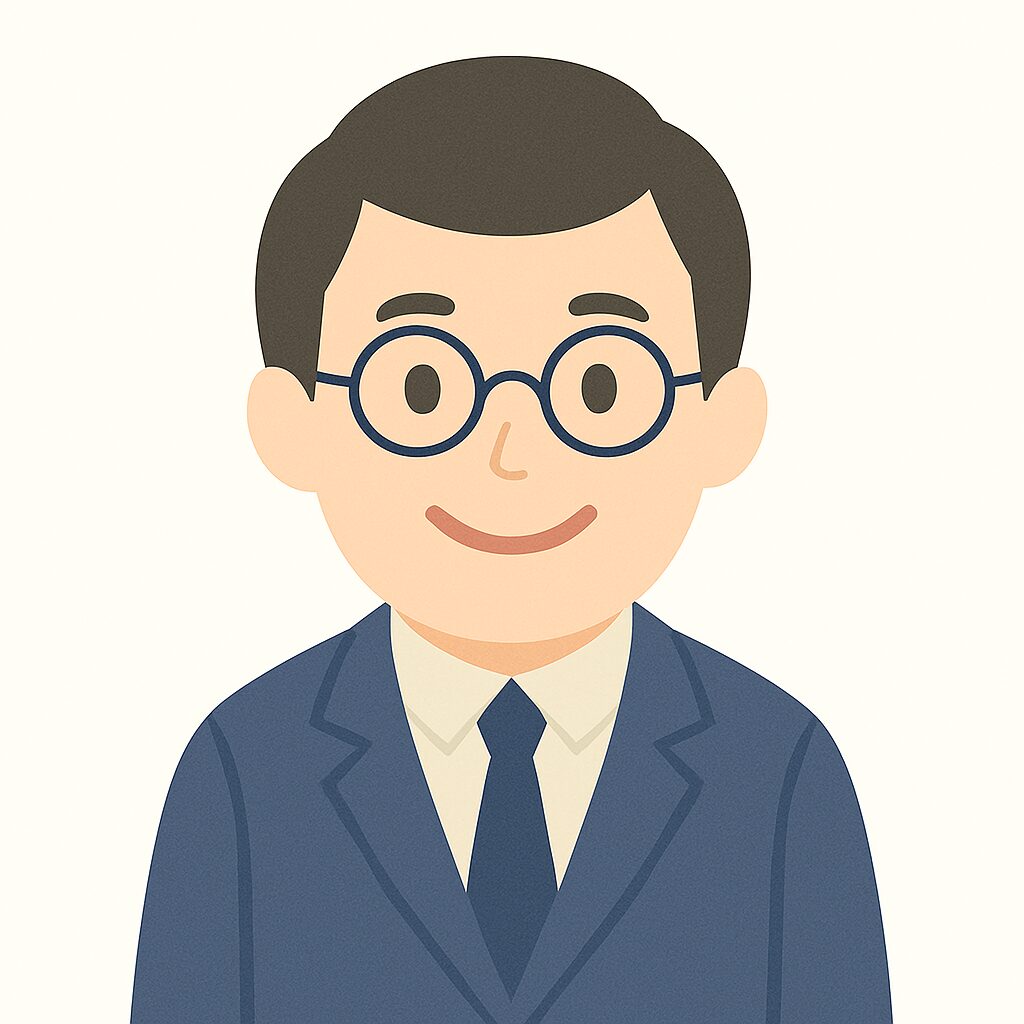
外部で採点を行うことで公平で客観的に評価され、生徒のスキルを統一した基準で評価できるということですね。
EAは校外で採点される試験と覚えておきましょう。
EAは成績の約7割を占める大切な試験
EAは成績の約70〜80%を占める、とても大切な試験です。
多くの科目でEAが全体の約7割、IAが約3割という配分が一般的となっています。
したがって「EAの完成度で最終成績の大部分が決まる」と言っても過言ではありません。
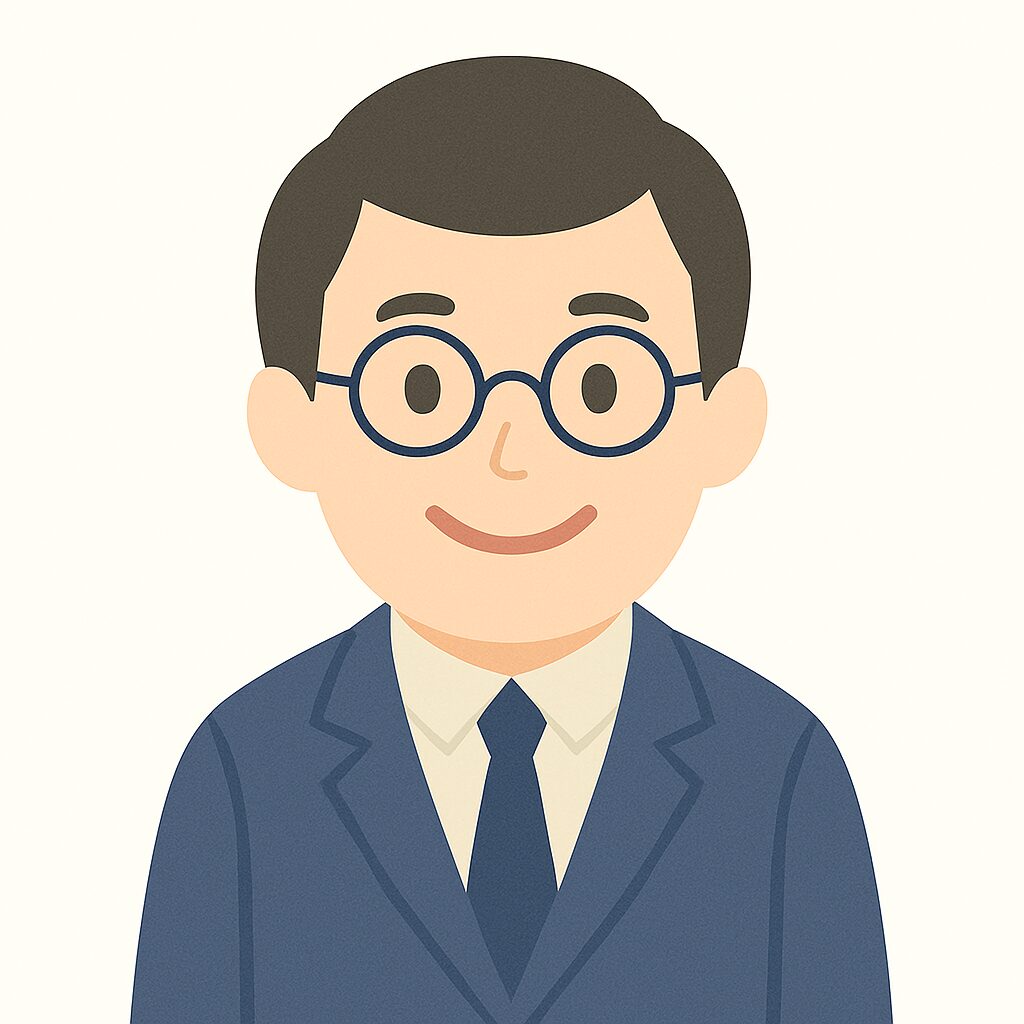
ただし科目によって配分は異なるため、履修科目ごとの割合を確認しておきましょう。
このためEA対策をすることは、IB成績で最も大切なステップになります。
IA(Internal Assessment)との違いは「採点者」と「成績の割合」
EAとIA(Internal Assessment:内部試験)の違いは以下2点です。
①採点者:EAは外部採点者、IAは学校の先生
②成績の割合:EAは全体の70〜80%、IAは20〜30%
IAは課題を学校の先生が採点する試験のことを言います。
IAを行う意味は、生徒の「普段の学習と理解」を評価するためです。
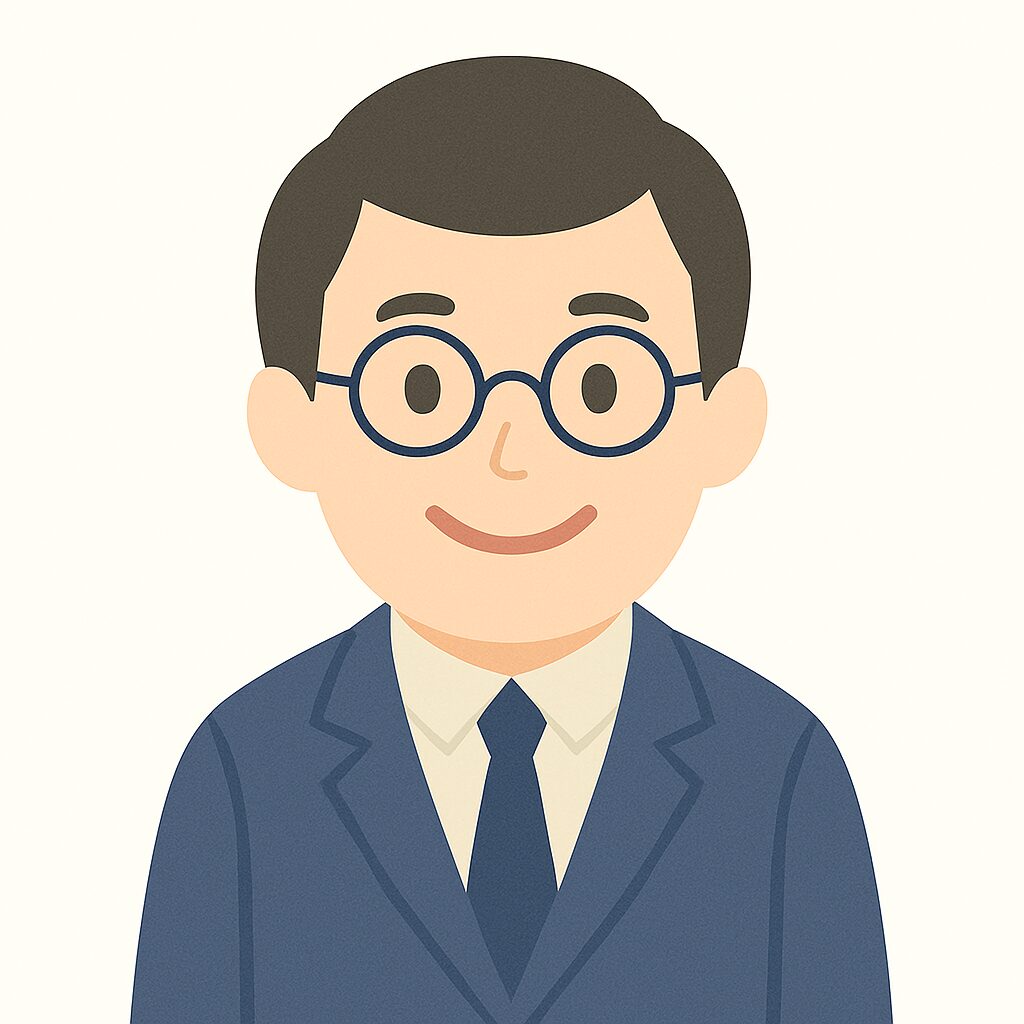
IAではレポートや実験記録などを生徒自身が作り、担当の先生が採点します。
ただすでに解説した通り、IAの成績は最終成績の20〜30%程度になることが多いです。
そのためEAよりも影響は限定されます。
「IAに力を入れなくていい」というわけではありませんが、EAに比べて成績の割合が少ない点を押さえておきましょう。
IB EAで必要な3つの力
EAは「知識をどう使いこなすか」が問われる試験です。
EAで特に必要な3つの力を整理し、どのように使うべきかを紹介しましょう。
知識を理解し活用する力
ただ知識を暗記するのではなく、問題解決や論述に応用する力がEAでは重要です。
EAの問題はただ知識を問うのではなく、「なぜそうなるか」「どう応用できるか」を問うものだからです。
たとえばEconomics(経済学)のEAでは、次のような問題が出ます。
Analyze the reasons for the rise in inflation in a certain country and its impact.
「ある国の物価上昇率が上がった理由と、その影響を分析しなさい。」
こういった設問に対し、知識を理論に当てはめて・具体例を挙げて・説明する力が求められます。
この力を鍛えられれば、EAで高得点が取れるだけでなく、今後の学び全体でも応用力が身につきます。
論理的に説明する力
論理的に説明し、読み手を納得させる文章力も大切です。
- なぜそうなるのか
- どんな背景があるのか
EAの設問はこういったことを問うものが多いため、ただ結論を書くだけでは説得力がたりません。
文章の構成としては、PREP法を意識しましょう。
PREP法はPoint(結論)・Reason(理由)・Example(具体例)・Point(結論)の頭文字を取った言葉で、この順番で書く方法です。
まず結論を述べ、その理由を示し、具体例で裏づけをして、再び結論を述べると、説得力がアップします。
例えばEconomicsで「価格上昇の原因」を問われたとすれば、以下のようになります。
PREP法
Point(結論)
価格上昇の主な原因は、需要の拡大と供給の制約です。
Reason(理由)
需要が拡大すれば、そのモノやサービスを買いたい人が増えるので価格が上がります。
また供給が制約されれば、提供できる量が減って希少性が強まるので、価格が引き上げられるのです。
Example(具体例)
たとえば世界の食料価格が上昇したのは、人口増加による需要の拡大、そして輸送コスト上昇など供給の制約が原因と考えられます。
Point(結論)
したがって「価格上昇の原因」は、「需要増加」または「供給制約」と考えられます。
このように論理的に説明ができれば、EAで得点を伸ばしやすくなります。
限られた時間で解答をまとめる力
時間内で論点を整理し解答をまとめる力も、EAで高得点を狙うためには重要です。
EAは定められた制限時間内で回答しなければなりません。
もし時間配分を間違うと、すべての設問を適切に答える余裕がなくなってしまい、得点が一気にダウンします。
たとえばEconomics SLの Paper 2(データ応答問題)は、1時間45分(105分)の制限時間です。
この場合、時間配分は以下のようになります。
①試験開始から最初の5~10分:
設問と図表・グラフを読み込み、どの設問に重点を置くかを決める
②次の3~5分:
各設問に対して下書き(論点のアウトライン)を作成
③70~80分:
文章を構成して記述
④残り5〜10分:
見直しをして、誤字脱字や論のつながりをチェックする
このような時間配分と構成力を意識して練習すれば、本番で慌てずに解答できるようになります。
【科目別】EAの試験形式と例
EAでは科目ごとに出題形式が大きく異なります。
そのため科目ごとの試験の特徴を理解しておくことが、効果的な学習のカギです。
ここでは代表的な科目におけるEAの形式例を紹介します。
言語科目:エッセイや読解問題が中心
Language A・Bなど言語科目のEAは、エッセイや読解問題で「文章を読んで自分の考えを論理的に書く力」を測ります。
ただの暗記ではなく「理解・分析・表現」の3つで評価するためです。
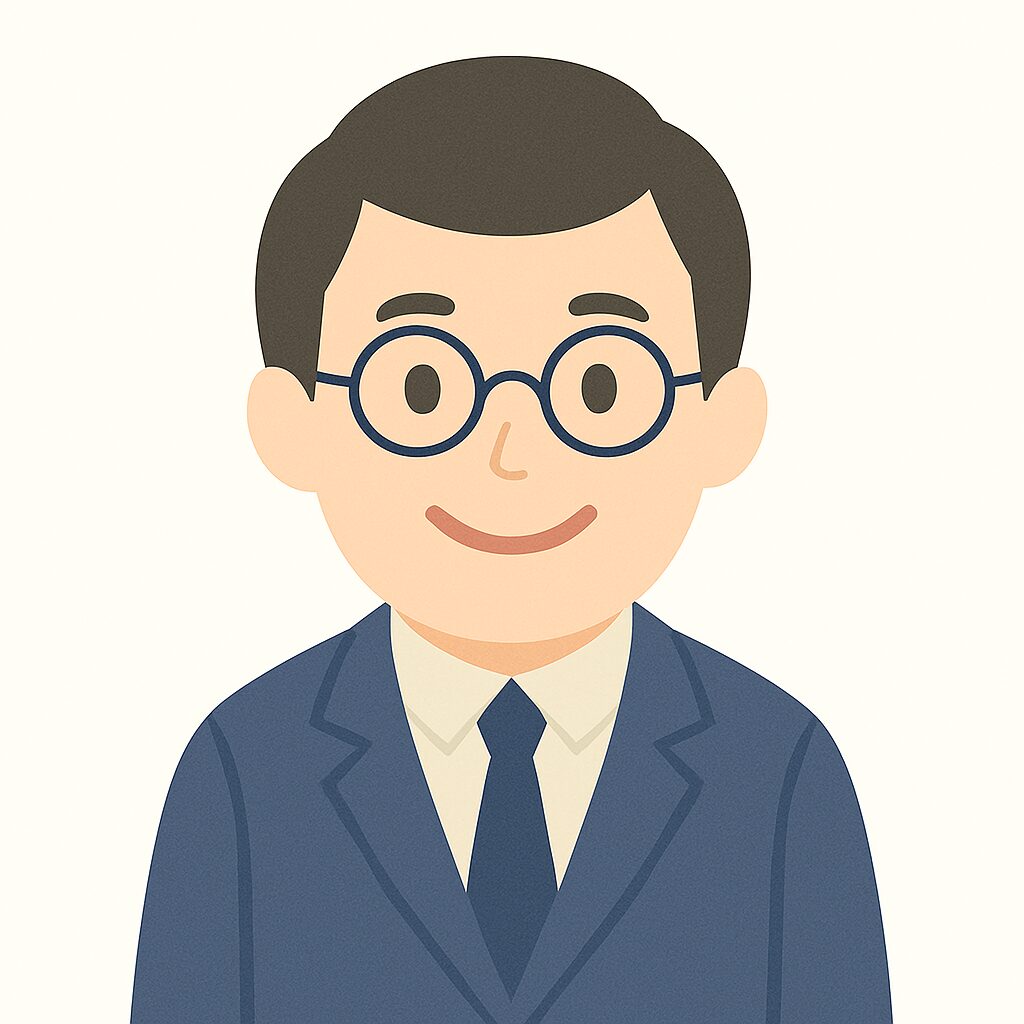
読解して内容を把握し、根拠を使って「どう理解したか」を説明できるかがポイントになります。
例:「Language A Literature」のPaper 1
- HL(Higher Level=高レベル)では2テキストを120分で分析。
- SL(Standard Level=標準レベル)では1テキストを75分で分析。
- 初見の文章・詩を読み、どう理解したかをエッセイとしてまとめる試験です。
- 登場人物の気持ちや行動を分析し、自分の視点を書くことが求められます。
言語科目での高得点のために、「読む力」と「書く力」をバランスよく鍛えましょう。
理数科目:計算問題や実験ベースの試験
Mathematics(数学)やChemistry(化学)など理数科目のEAでは、計算問題や実験データをもとに考察する形式が中心となります。
理科・数学分野では「公式や理論を使って説明する力」や「実際データを読み解く力」が求められるからです。
例:Physics (物理)の Paper 2
- 120分で、計算問題と記述問題を組み合わせた問題が複数出されます。
- 力学・熱・電磁気などの公式を使い、計算の答えや「現象・実験データとどうつながるか」を記述する解答も必要です。
理数科目のEAでは公式や理論の暗記だけでなく、「計算力」「データ処理力」「考察力」の3つを組み合わせて練習しましょう。
人文社会科目:論述や資料分析問題
Geography(地理)やEconomics(経済)など人文・社会科目のEAでは「資料を読み解き、自分の考えを整理して説明する力」が問われます。
資料(文献・統計データ・地図など)を使い、自分の考えを説得力を持って示すスキルを評価するからです。
例:History(歴史)のPaper 2
- 「ある戦争の原因を、複数の要因から論じなさい。」「冷戦における政策の影響を比較しなさい」といった論述問題が出題されます。
- 加えて資料(演説の抜粋、統計表、地図など)が与えられ、それを元に質問に答える形式も含まれています。
人文社会科目のEAで高得点を取るためには、資料を読解できる力、それをもとに論述する力を鍛えることが大切です。
IB EA対策で行うべきポイント
EAは成績全体の7割を占めるため、計画的な対策が大切です。
ここではEA対策として、特に効果的なポイントを紹介します。
過去問を使った時間配分の練習
まずは過去問を使い、本番と同じ時間配分で解く練習をしましょう。
本番と同じ時間配分での練習は、途中で時間切れになってしまうリスクと緊張を取り除いてくれます。
たとえば以下のように、時間配分を決めておきましょう。
- 設問読解に10分
- 各設問に30分ずつ
- 最後に10分見直し
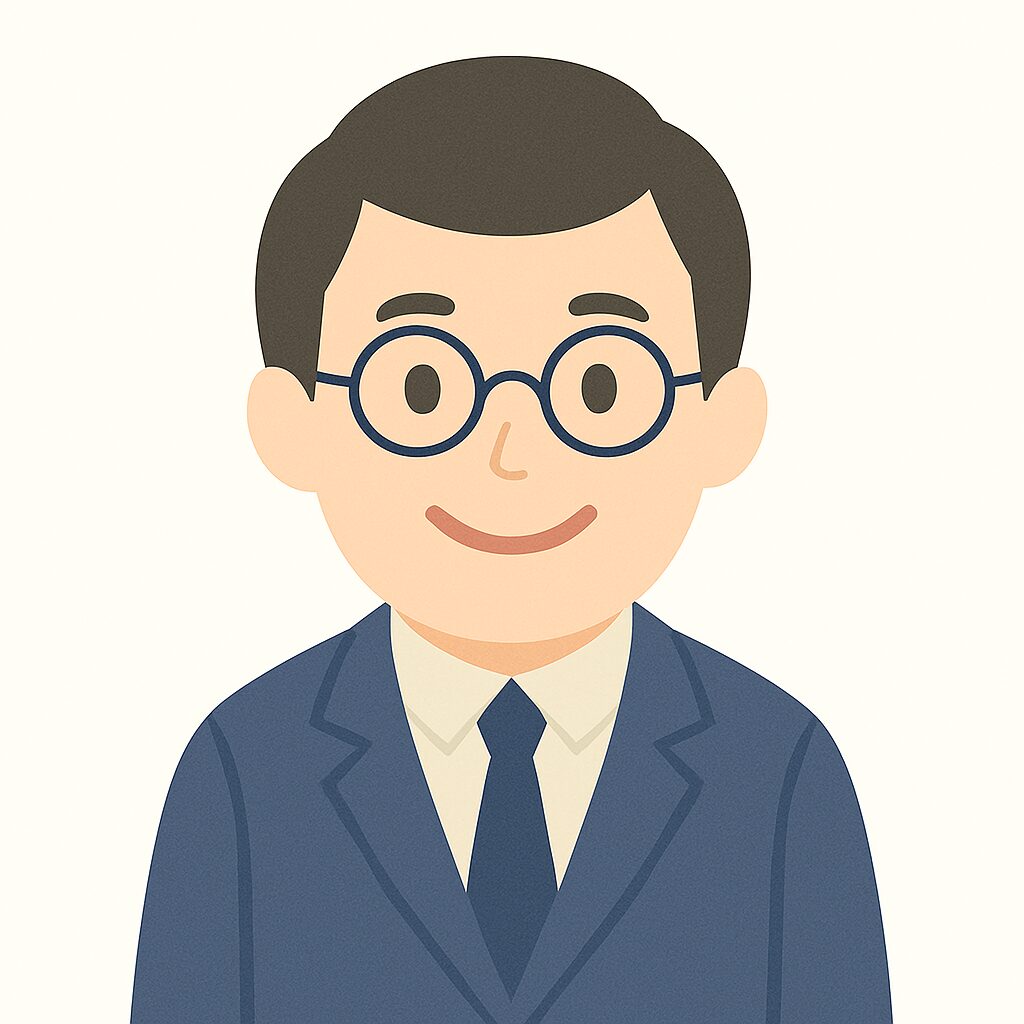
科目によってベストな時間配分は異なるので、過去問を通じて自分に合ったリズムを見つけましょう。
時間配分を決めた練習を繰り返せば、本番でも焦らずに解答を進められるようになります。
採点基準(マークスキーム)の理解
マークスキームという採点基準を理解しておくことが、得点アップの分かれ目となります。
マークスキームは設問ごとに「何をすれば何点取れるか」を細かく定めたものです。
それを意識して解答を書くことで、ムダな答えを減らせます。
たとえばChemistry(科学)のマークスキーム例は次の通りです。
- 説明は「なぜそうなるのか」を順序よく書けているか
- 途中の式や単位を省かずに書けているか
- 実験データは文章だけでなく、グラフや表にまとめているか
- 実験で出た結果を「理論と比べてどうか」を説明できているか
評価者はこの軸に沿ってスコアをつけるため、そのことをきちんと意識すると点が伸びやすくなります。
EAとIAをつなげて学習効率アップ
EAとIAを関連づけて学習すると、効率よくスコアを伸ばすことが可能です。
EAとIAでは、出題テーマや評価の方向性と重なる部分があります。
つまりIAの知識・構成の練習が、EAでの論述力や論点整理力の強化につながるのです。
例えばいずれかの科目のIAでレポートを書いたとします。
そのレポートの構成(背景 → 因果関係 → 評価)は、EAで出る問いの形式でも使えます。
またIAで資料分析や一次資料の扱いに慣れておくと、EAの資料の扱いにも対応しやすくなります。
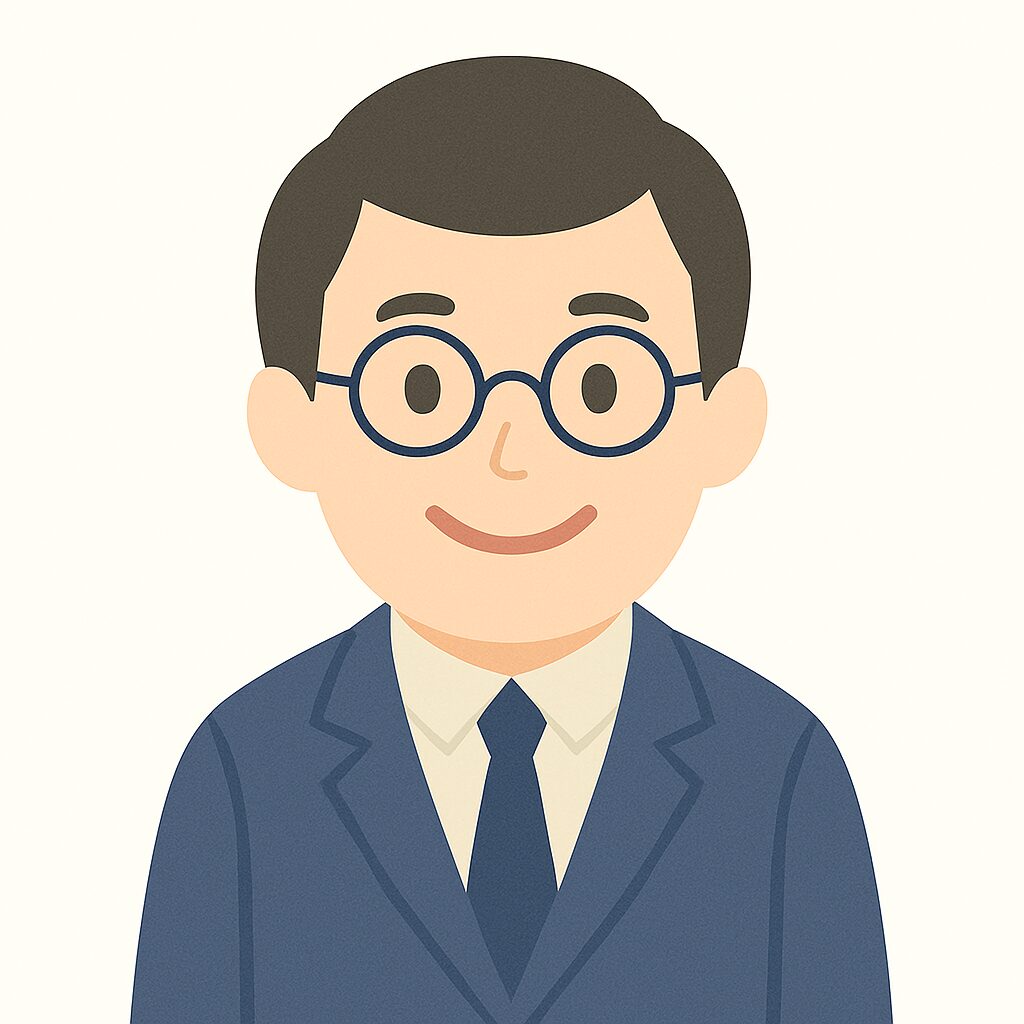
IAの構成力や資料の扱いを、EAの準備に活かすわけですね。
IAをただこなすだけではなく「EAを意識してIAに取り組む」ことで、構成・思考力が連動し、学習効率がアップするのです。
試験の前にできるEA対策
EA当日を安心して迎えるためには、事前の練習や準備をしっかり行うことが欠かせません。
ここでは試験前に取り組める、具体的なEA対策を紹介します。
「試験の環境(時間・場所・持ち物)」を再現
EA本番で緊張しないために、試験環境を再現して慣れておくととても効果があります。
「どのような流れで問題を解き、どう過ごせばいいか」が練習できるからです。
過去問を使って時間配分を考える以外にも、下記を再現しましょう。
- 試験会場のような静かな場所を選ぶ(学校の教室や図書館など)
- ペン・定規・計算用紙などを準備し、本番同様に使えるようにする
このような本番想定の練習をしておけば、当日も落ち着いて解答できるようになり、スコアアップを最大化できます。
成績のフィードバックから考える「改善プラン」
EAの結果を確認するだけでは、成績はアップしません。
試験後に戻ってくるフィードバックを使い、改善プランを立てることが重要です。
フィードバックには弱点や改善点が示されており、同じミスを防止するために使えます。
たとえばEAで、次のようなフィードバックがあったとしましょう。
- 論点の提示が弱い
- 分析が浅い
そうした場合、改善プランとして以下のように考えられます。

・主張→理由→補足を意識して書き、論点を分かりやすくする練習をしよう!
・資料やデータを使って裏付けし、分析を深めるトレーニングを取り入れる!
こうしたフィードバックからの反省を、練習や模試に落とし込み実行すれば成果が出やすくなります。
IB EAを理解して得点アップを狙おう
「IBのEAの基礎と対策方法」をわかりやすく解説しました。
- EAは成績の約7割を占めるため、早めに準備することが大切
- 科目ごとの試験形式を把握し、必要な力を意識することが得点アップにつながる
- 試験環境の再現・フィードバックを活かした改善プランで、安心感と実力発揮を後押し

・EAの勉強法をどう子どもに教えればいいの?
・過去問をやっても成績が伸びなくて不安…
・志望大学に必要な点数を知りたい!
こんな悩みをお持ちなら、IB専門塾IBアカデミーの個別指導や進路指導を活用しましょう!
専門の先生がお子様に合わせた学習法を提案してくれるので、安心してEAの対策ができます。





