
IB UOIで身につく3つの力|家庭でできるサポート方法も解説


・UOIって何?どんな授業なのか知りたい!
・従来の教育と何が違う?本当に将来に役立つの?
・家庭ではどんなサポートをすればいいんだろう?
UOI(Unit of Inquiry:探究の単元)は一見わかりにくいシステムなので、どのように取り組めばいいか悩みますよね。
この記事を読めばUOIの基本・評価方法・家庭でできる関わり方まで理解できます。
IB専門塾のIBアカデミーでは、世界トップレベルのIB卒業生による個別指導を受けられるため、学び方や家庭でのサポート方法も相談可能です。
一人ひとりに合わせた学習計画と進捗(しんちょく)管理、完全オンライン対応のサポート体制が整っているので、お子様にベストな学習環境を実現できます。
目次
IBのUOIの基本ポイント4つ
まずは「UOIの意味と目的」「UOIで身につく力」「探究サイクル」「テーマ」について解説します。
UOIの意味と目的
UOIとは、PYP(IBの初等教育)における「子どもが自ら問いを考え、その答えを探しながら学ぶ授業のしくみ」のことです。
例えばプロボケーション(Provocation)という取り組みがあります。
これは「ちゃんとしているようで、でもどこかおかしい画像や問いかけ」などを子どもに投げかけ、おかしいポイントを探させることで、好奇心を刺激します。

・どうしてそうなるんだろう?
・何がおかしいのかな?
このような考えを子どもにさせることで、自分から考えるきっかけとなるのです。
「ただ知識を詰め込むのではなく、学びを実生活につなげるしくみ」がUOIであり、子どもが自分で考える力となります。
UOIで育つ3つの力
UOIを通して身につく力は以下の3つです。
UOIで身につく力
① 自分で考えて行動する自律性
② 複数の教科をつなげて考える視点
③ 他者と協力し相手を尊重する姿勢
これらは暗記中心の学びでは手に入りにくく、自分で考えて行動するUOIの中で自然と身についていきます。
学んだ知識を社会で活かすためのしくみがUOIです。
子どもが主体的に学ぶ「探究サイクル」
UOIの探究サイクルとは、「自分で考えて学ぶ力」を身につけるための流れのことです。
先生の説明だけに頼って勉強するのではなく、「自分で疑問を持ち、調べ、考え、行動する」を繰り返すことで、自分ごととして学べるようになります。
探求サイクル
① まず気になることを見つける(Tuning In)
② 本やネットで調べる(Finding Out)
③ 情報を整理する(Sorting Out)
④ 深く掘り下げて考える(Going Further)
⑤ 自分なりの答えをまとめる(Making Conclusions)
⑥ 学んだことを行動に移す(Taking Action)
この流れを繰り返すことで、「手に入れた知識を使って考え、行動する力」が自然と身につくのです。
UOIで扱う6つのテーマ
UOIを通して学ぶテーマは6つあります。
UOIテーマ
① 「Who we are(私たちは誰か)」
「自分とは何か」を問いながら、自分と他者の違いや人間関係を理解し、自己認識と共感力を育てる
② 「Where we are in place and time(時間と場所の中の私たち)」
歴史や文化を探究し、自分と世界のつながりを理解して視野を広げる
③ 「How we express ourselves(自己表現の方法)」
自己表現の方法などについて学び、自分の考えを伝えるコミュニケーション力を身につける
④ 「How the world works(世界の仕組み)」
自然・社会のしくみ・科学技術の影響を探究し、「考察力」「理解力」「問題分析力」を高める
⑤ 「How we organize ourselves(社会のしくみ)」
社会構造・組織・経済活動を学び、社会に存在するしくみへの理解と分析力を深める
⑥ 「Sharing the planet(地球を共有する)」
限られた資源・環境の中で共存する大切さを学び、公正さや持続可能性への意識を育てる
これらのテーマを、国語や理科などの教科を横断して学んでいきます。
なぜなら現実社会の課題は一つの教科の知識だけでは解けないことが多く、複数教科の知識や考え方をつなげて考える必要があるからです。
これらのテーマを軸に学びを深めることで、より広い視野で考えられるようになります。
IB UOIと従来の教育の違い
UOIは従来の教育と比べ、「学び方」「教育のゴール」「評価方法」が大きく異なります。
ここではその違いを整理して解説します。
学び方の違い【知識の暗記から探究型へ】
UOIは自ら考えて行動する「探究型」の学び方なので、従来の教育よりも自分から学びに向かう姿勢を身につきます。
従来の教育では「丸暗記してテストで答える」ことが重視されてきました。
ですがUOIでは「なぜそうなるのか」を自分で考え、調べ、納得したうえで表現できるようになることが大きな目標です。
その実現のために、探究型の学びは大いに役立ちます。
ただ正解を記憶するだけではなく、実生活や将来に活かせる力がUOIで身につくのです。
ゴールの違い【点数重視から将来につながる力の育成へ】
UOIはテストの成績だけでなく、社会で役立つ思考力・主体性を育てることをゴールにしています。
なぜならIBの教育目標は知識の暗記ではなく、「学んだことを使って社会の問題を解決する力」を育てることだからです。
例えばグレード3では、「生活習慣の選択が健康に与える影響」というテーマを中心に各教科にてUOIが実施され、自分の行動が健康につながることに気づく探究活動に取り組みます。
こういった取り組みにより、生徒は「考える力」「行動力」「社会との関わり」を身につけ、点数には表れない主体的な成長を実現できるようになるのです。
評価方法の違い【ペーパーテスト中心から多面的評価へ】
IBではペーパーテストだけでなく、いろんな課題や活動を通して理解や成長を評価します。
知識を学んでテストする従来の方法では、UOIが目指す「主体的な学び」は身につきにくいからです。
- 授業中の課題
- リサーチ課題
- CAS活動
- プレゼンテーション
これらペーパーテスト以外の課題・活動で、学びへの主体性が評価されます。
いろんな角度からの評価により、テストの点数以上に「どんな力が育ったか」がしっかり把握できるようになるのです。
お子様の成長が把握できるIB UOIの評価方法
「UOIでの学習成果が、どのような見える形で示されるのか」を知ることは、保護者様にとっても安心につながります。
ここでは評価のしくみと成長の記録方法を紹介します。
UOIの成績評価方法と基準
すでに解説した通り、UOIではテストの点数だけでなく、課題や活動を通して評価されます。
その課題・活動の「過程」と「成果」の両面を評価するしくみです。
UOIの評価基準
形成的評価(Formative Assessment)
・授業中の活動や調べ学習を評価する
総括的評価(Summative Assessment)
・単元の最後に成果をまとめて確認し評価する
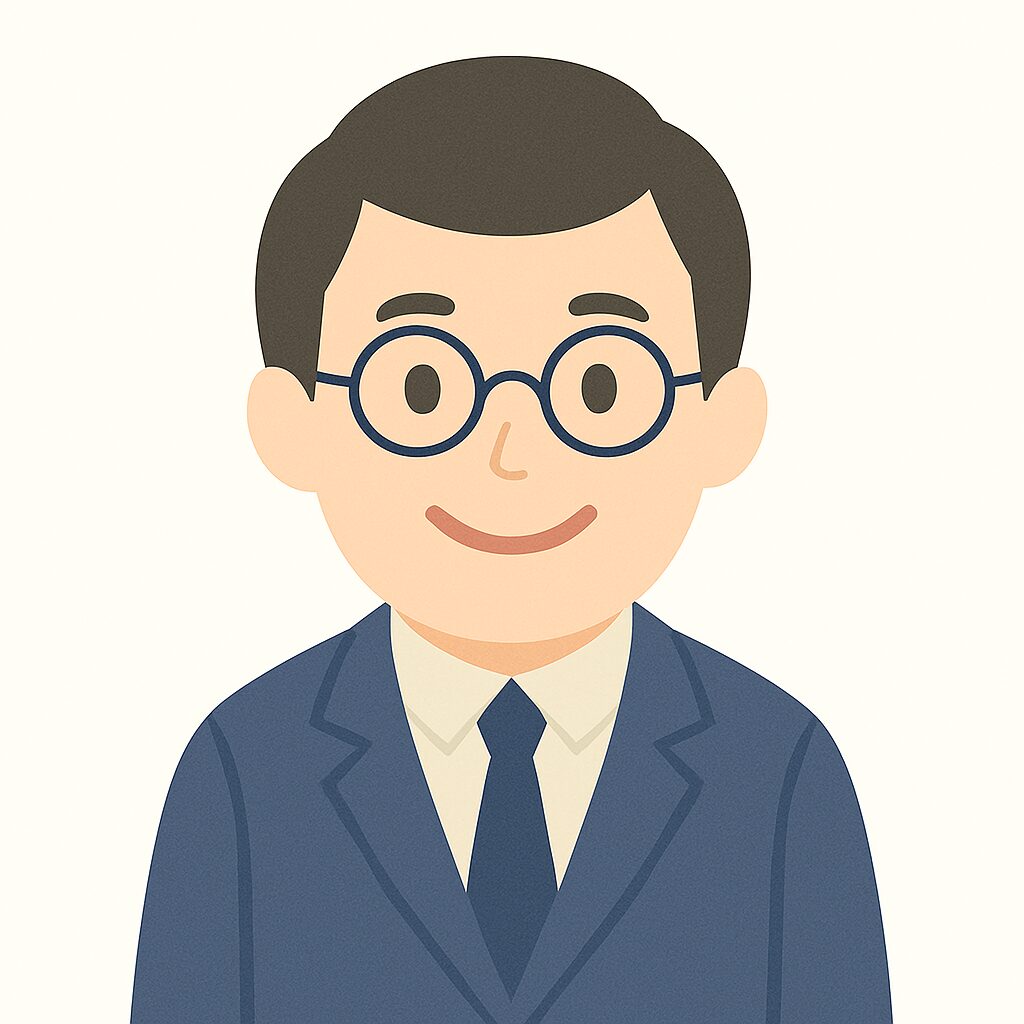
例えば探究の途中での意見交換やワークシートの記録が形成的評価、最終的なプレゼンテーションやレポートが総括的評価の対象となります。
こうした基準により、「子どもがどう考えて成長したか」を詳しく把握することが可能です。
ポートフォリオと発表会で見える学びの成果
UOIで学んだ過程・成果を確認できる手段として、ポートフォリオと発表会(エキシビション)があります。
テストだけでは測れない「考える力」や「表現力」などを評価する必要があるので、活動や過程の記録を見える形にするためのものです。
ポートフォリオ
- 選んだ作品や振り返りを書き込んだ、学習の記録・まとめ
- 学びの積み重ねが見える
発表会(エキシビション)
探究の成果をまとめて発表し、学んだことを周りと共有する
こうした形式で「考えたこと」「学んだプロセス」を見えるようにしているので、お子様と保護者に安心感や達成感が湧きます。
IB UOIを家庭で育てる3つのサポート方法
学校の授業だけではなく、家庭での関わりがUOIの学びをさらに深めます。
ここでは家庭でできるサポート方法を3つ紹介します。
探究テーマについて親子で一緒に調べる
UOIで扱うテーマを親子で一緒に調べることは、学びを深めるだけでなく、会話を通して思考力・共感力を育てる機会になります。
一方的に親が教えるのではなく、一緒に考えたり、おたがいに質問しあったりすることは、子どもの主体的な学びを育てるのに効果的です。

・どんな方法で調べたらいいと思う?
・この出来事とさっき調べたことって、どんなつながりがあるかな?
・他の国の子が同じテーマを調べたらどんな意見になるかな?
こうした会話をすることで、子どもが考える習慣が育ち、学びへの主体性が身につきます。
日常のできごとを質問で深める
IBの勉強以外でも、日常の何気ない質問で思考力を育てられます。
普段から身近なできごとに関係する問いを投げかければ、子どもが「なぜだろう?」と考える習慣がつき、そのまま勉強への自主性につながるからです。
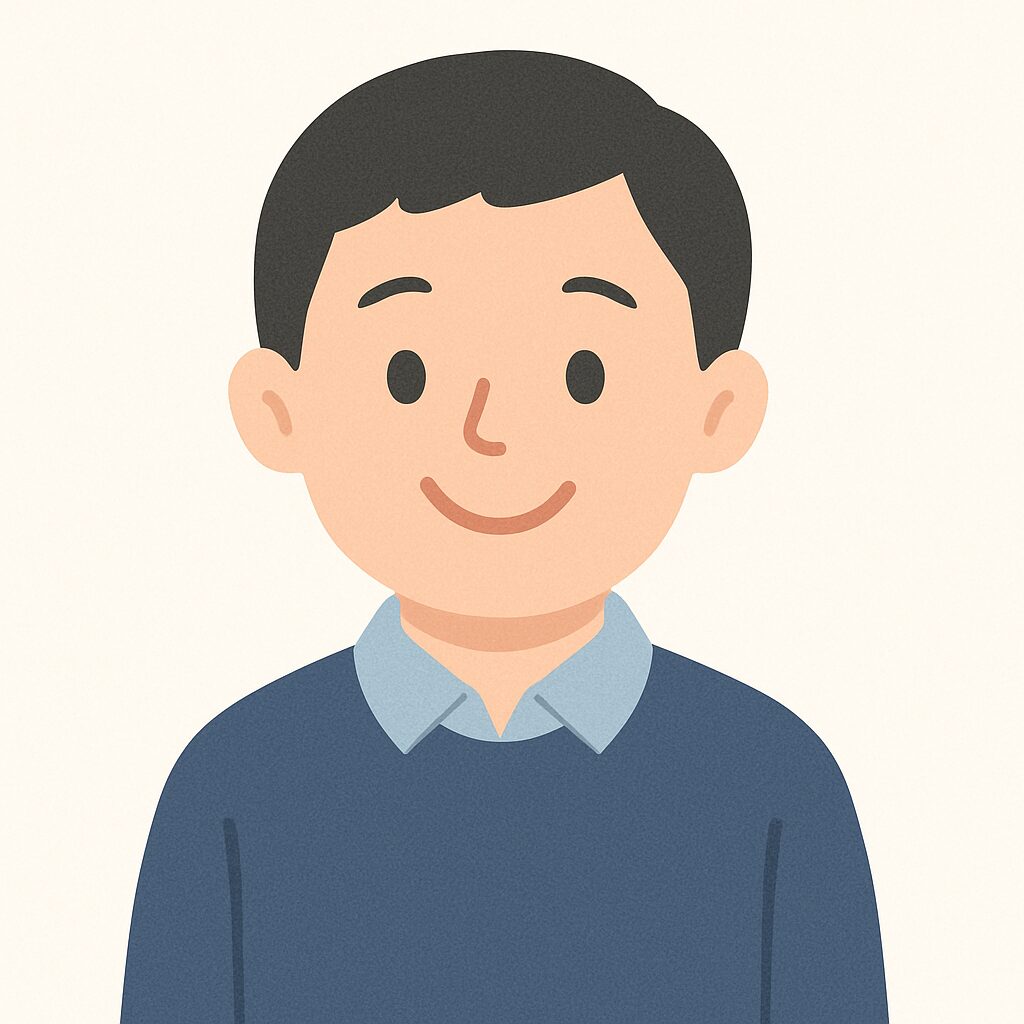
・どうして夕焼けの色は変わるのだと思う?
・お風呂に入れている石けんが浮くのはなぜかな?
こういった問いかけは好奇心を刺激し、観察と思考を促してくれます。
このようなやり取りを日常に取り入れ、子どもが自然に「探究のサイクル」を体験できる習慣をつけていきましょう。
学校での学びを家庭で振り返る
学校で勉強したことを家庭で一緒に振り返ると、より確実にUOIの効果が伸びていきます。
「今日の授業の振り返りをしよう」と、自主的に思える子どもはほとんどいません。
保護者が一緒に振り返ることで、自分の考え方や行動を意識できるようになります。

今日は学校でどんな新しい発見があった?
こんなふうに声をかけるだけでも、子どもは自分の理解や課題を整理できます。
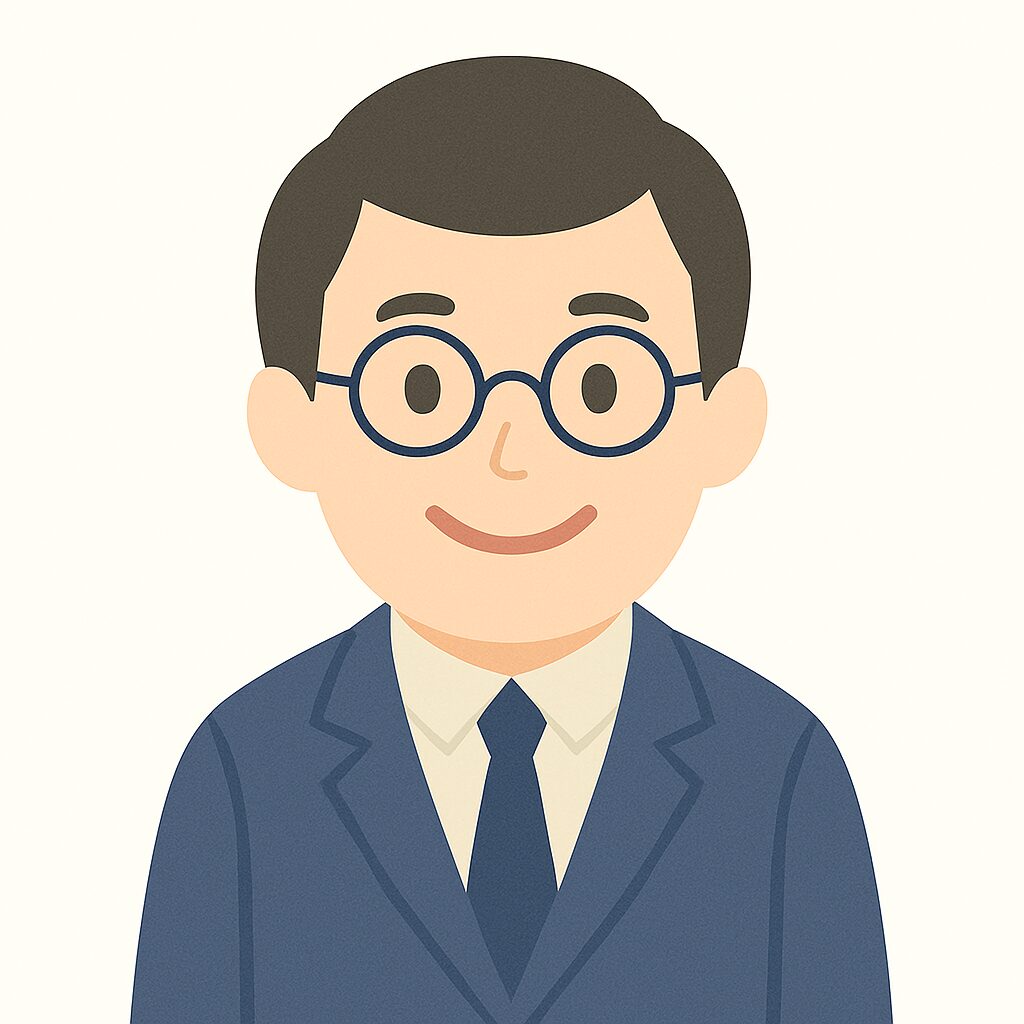
さらに「学校で感じた疑問をどうやって調べようか?」と聞くことで、自主的な学びがさらに促されますよ。
家庭で振り返る習慣を重ね、UOIの成果をしっかり身につけていきましょう。
IBでのUOIに取り組んで将来役立つ力を身につけよう
「IB UOIの基本・特徴・家庭でのサポート方法」を解説しました。
UOIまとめ
- UOIは点数ではなく、思考力・自律性・協働性を育てる仕組み
- テストだけでなく、過程や成果を大切にすることが子どもの成長につながる
- 家庭での問いかけや振り返りから、学校での学びを日常に結びつける姿勢が大切
- 子どもの探究心を尊重し、親が一緒に考える姿勢が重要
- 将来につながる力を育てるために、家庭と学校が連携しよう

・評価の基準がよく分からない…
・家庭でどうサポートすればいいのか不安…
・進路にIBの学びがどうつながるのか知りたい!
こうした悩みをお持ちの方は、IBアカデミーの個別指導・進路相談をぜひご活用ください。
お子様にベストな学び方を一緒に設計していきましょう。




